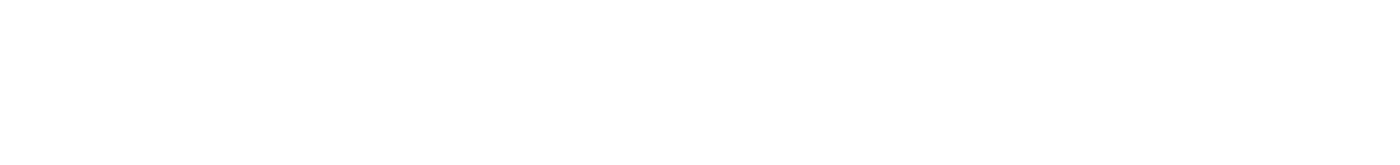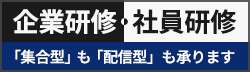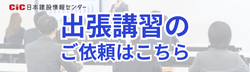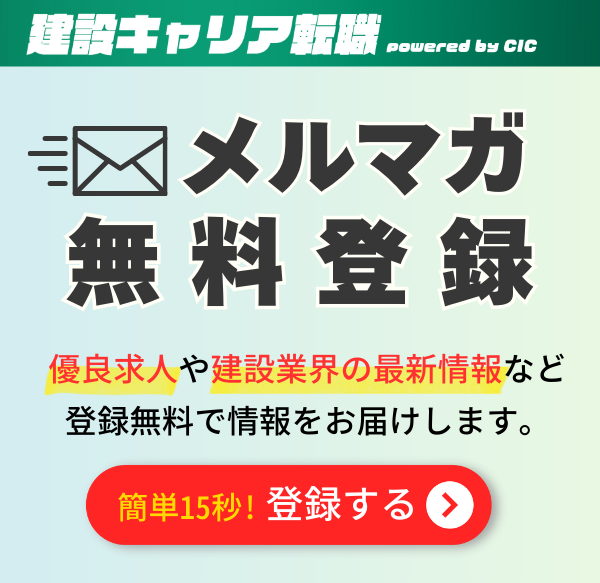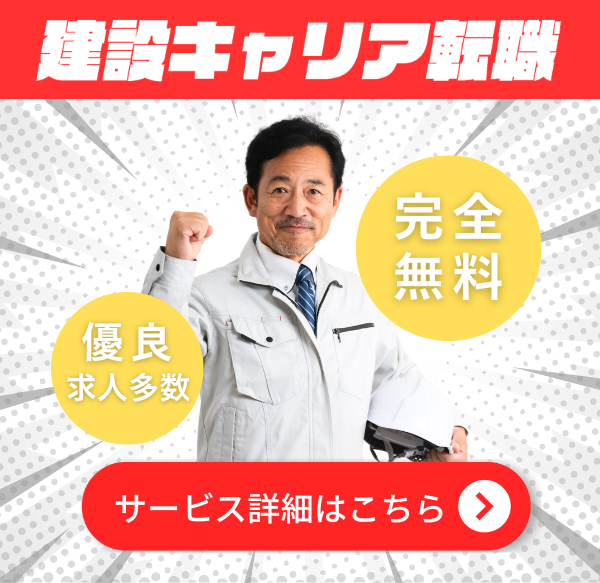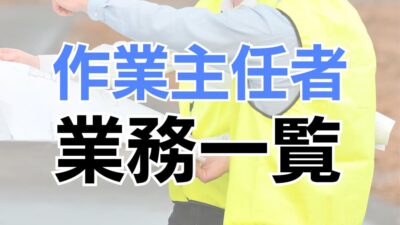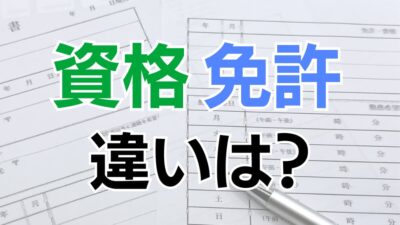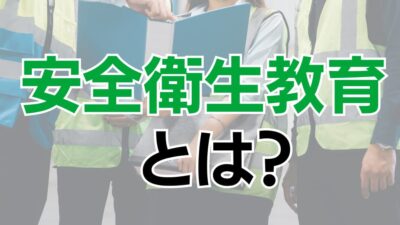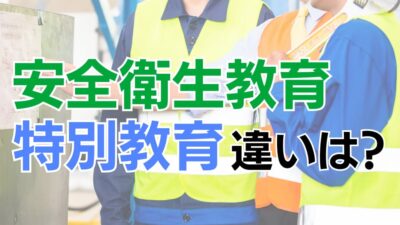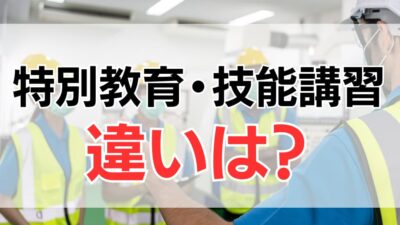施工管理技士合格をアシスト
建設業特化の受験対策
特別教育とは?実施方法や内容、修了証の発行などやさしく解説
公開日:2023年12月27日 更新日:2025年3月21日
特別教育とは?実施方法や内容、修了証の発行などやさしく解説
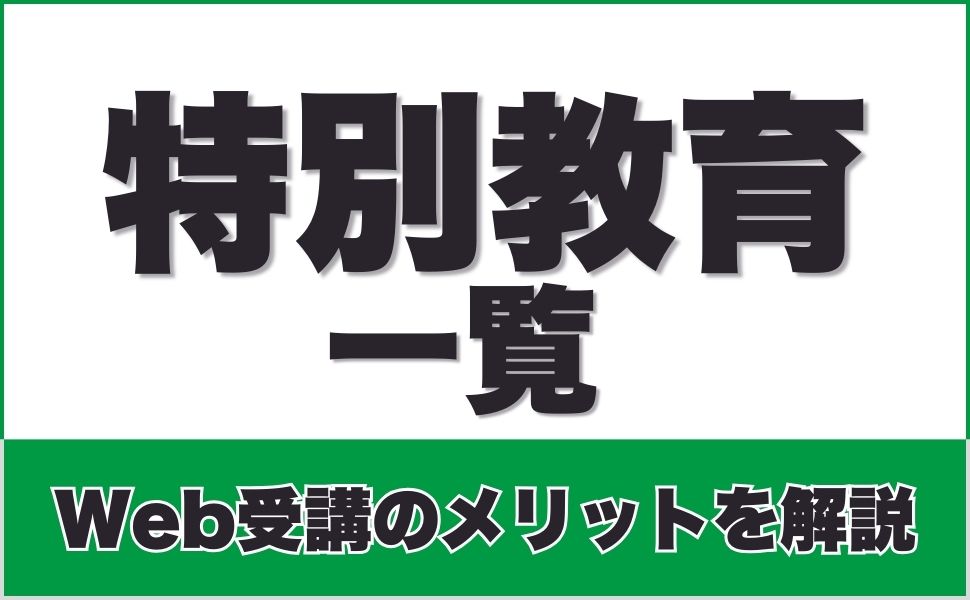
特別教育は、特定の危険性を伴う業務を行う場合に必要な専門的な教育を指します。
労働安全衛生法により、「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない」と定められています。
この記事では各特別教育をどのように実施したら良いのか、修了証の発行は?などそれぞれの疑問をやさしくていねいに解説します。
目次
特別教育とは

「特別教育」とは、特定の危険性を伴う業務を行う場合に必要となる専門的な教育のことを指しています。
具体的には、労働安全衛生法で「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。」と定められています。
なお、「技能講習(作業主任者含め)」は法令に基づく国家資格ですが、 「特別教育」「安全衛生教育」は国家資格には該当しません。
特別教育が必要な業務
特別教育が必要とされるのは、労働安全衛生規則第36条で規定されている、アーク溶接や小型車両系建設機械(フォークリフトやクレーンなど)の運転、酸素欠乏危険作業などを含む49の業務です。
特別教育を必要とする危険有害業務
特別教育を必要とする危険有害業務を紹介します。
| No. | 対象業務 |
|---|---|
| 1 | 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務 |
| 2 | 動力プレスの金型、シャーの刃部又はプレス機械・シャーの安全装置・安全囲いの取付け、取外し又は調整の業務 |
| 3 | アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務 |
| 4 | 高圧(直流 750V 超・交流 600V 超~7,000V 以下)・特別高圧(7,000V 超)の充電電路・その支持物の敷設などの業務。低圧(直流 750V 以下・交流 600V 以下)の充電電路(対地電圧 50V 以下及び感電による危害を生じるおそれのないものを除く。)の敷設、修理の業務等 詳細は労働安全衛生規則第36条第4号参照 |
| 4の2 | 対地電圧が50ボルトを超える低圧の蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務 |
| 5 | 最大荷重1トン未満のフォークリフト運転業務(他に道交法適用有り) |
| 5の2 | 最大荷重1トン未満のショベルローダー、フォークローダー運転業務(他に道交法適用有り) |
| 5の3 | 最大積載量が1トン未満の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 |
| 5の4 | テールゲートリフターの操作の業務 |
| 6 | 制限荷重5トン未満の揚貨装置運転業務 |
| 6の2 | 伐木等機械の運転業務(他に道交法適用有り) |
| 6の3 | 走行集材機械の運転業務(他に道交法適用有り) |
| 7 | 機械集材装置の運転業務 |
| 7の2 | 簡易架線集材装置の運転業務・架線集材機械の運転の業務 |
| 8 | チェンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務 |
| 9 | 機体重量3トン未満の不特定場所を自走できるものの運転業務(他に道交法適用有り)
|
| 9の2 | 令別表7の3号(基礎工事機、上記参照) 自走できないものの運転業務 |
| 9の3 | 同上(同上)自走できるものの作業装置の操作業務 |
| 10 | 令別表7の4号(締固め用機械)ローラー運転業務(他に道交法適用有り) |
| 10の2 | 令別表7の5号(コンクリート打設用機械)作業装置の操作業務 |
| 10の3 | ボーリングマシン運転業務 |
| 10の4 | 建設工事の作業で使用するジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転業務 |
| 10の5 | 作業床の高さが10m未満の高所作業車の運転の業務(他に道交法適用有り) |
| 11 | 動力駆動の巻上げ機の運転業務(電気ホイスト・エアーホイスト・これら以外の巻上げ機でゴンドラに係るものを除く) |
| 13 | 令第15条第1項第8号の軌道装置等運転業務(除く鉄道事業法又は軌道法適用のもの) |
| 14 | 小型ボイラー取扱業務 |
| 15 | つり上げ荷重5トン未満のクレーン・つり上げ荷重5トン以上の跨線テルハの運転業務(除く移動式クレーン) |
| 16 | 移動式クレーン(つり上げ荷重1トン未満)の運転業務(他に道交法適用有り) |
| 17 | デリック(つり上げ荷重5トン未満)の運転業務 |
| 18 | 建設用リフトの運転業務 |
| 19 | 玉掛業務(1トン未満のクレーン、移動式クレーン及びデリック) |
| 20 | ゴンドラの操作業務 |
| 20の2 | 作業室、気こう室へ送気するための空気圧縮機の運転業務 |
| 21 | 高圧室内作業に係る作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコックの操作業務 |
| 22 | 気こう室への送気・排気の調整を行うためのバルブ又はコックの操作業務 |
| 23 | 潜水作業者への送気調節を行うバルブ又はコックの操作業務 |
| 24 | 再圧室の操作業務 |
| 24の2 | 高圧室内作業に係る業務 |
| 25 | 四アルキル鉛等業務(令別表第 5 の四アルキル鉛等業務) |
| 26 | 酸素欠乏危険場所における作業に係る業務(令別表第 6 の酸素欠乏危険場所) |
| 27 | 特殊化学設備の取扱い、整備及び修理業務(除く第一種圧力容器) |
| 28 | エックス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影業務 |
| 28の2 | 加工施設、再処理施設又は使用施設等の管理区域における核燃料物質又は使用済燃料(汚染物を含む)の取扱業務 |
| 28の3 | 原子炉施設の管理区域内における核燃料物質又は使用済燃料(汚染物を含む)の取扱業務 |
| 28の4 | 東日本大震災に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質により汚染された物であって、電離則第2条第2項に規定するものの処分の業務 |
| 28の5 | 電離則第7条の2第3項の特例緊急作業に係る業務 |
| 29 | 粉じん則第2条1項3号の特定粉じん作業に係る業務 |
| 30 | ずい道等の掘削作業、ずり、資材等の運搬、覆工のコンクリート打設等の作業に係る業務 |
| 31 | 産業用ロボットの可動範囲内において行う教示等又はそれらを行う労働者と共同して可動範囲外にて行う当該教示等に係る機器の操作業務 |
| 32 | 産業用ロボットの可動範囲内において行う検査等又はそれらを行う労働者と共同して可動範囲外にて行う当該検査等に係る機器の操作業務 |
| 33 | 空気圧縮機を用いて行う自動車(除く2輪自動車)のタイヤの空気充てん業務 |
| 34 | 廃棄物焼却施設(ダイオキシン類特別措置法)におけるばいじん、焼却灰等を取り扱う業務 |
| 35 | 廃棄物焼却施設の焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務 |
| 36 | 廃棄物焼却施設の焼却炉、集じん機等の設備の解体等の業務及びこれに伴う焼却灰等の取扱業務 |
| 37 | 石綿等が使用されている建築物等の解体等の作業並びに石綿等の封じ込め、囲い込みの作業 |
| 38 | 土壌等の除染等の業務及び特定線量下業務 |
| 39 | 足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。) |
| 40 | 高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、昇降器具を用いて行うロープ高所作業に係る業務/td> |
| 41 | 高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く。) |
引用:厚生労働省
特別教育を行わなかった場合
では、もし特別教育を受けなかった場合はどうなってしまうのでしょうか。
特別教育を受けない場合、以下のリスクが考えられます。
法令違反
労働安全衛生法や労働基準法に基づいて特定の業務で特別教育を受けることが義務付けられています。法令遵守を怠ると、法的な問題が生じる可能性があります。
- 特別教育が必要な作業者にその教育を実施していない場合:6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
- 無資格の作業者を就業させた場合: 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
労働災害の発生
特別教育を受けないと、危険な作業を行う際に適切な知識やスキルが不足してしまいます。結果として、労働災害が発生するリスクが高まります。
職場での信頼低下
特別教育を受けないと、他の労働者や上司から信頼されにくくなる可能性があります。安全な作業環境を共有するためには、適切な知識とスキルを持つことが重要です。
キャリアの制限
特別教育を受けないと、資格や免許を取得できない場合があります。これはキャリアの成長に制限をもたらす可能性があります。
特別教育を受けることで、労働者の安全とスキル向上を促進し、職場での信頼を築くことができます。
特別教育の実施方法
特別教育は外部機関を利用する方法と、自社内で行う方法の2つがあります。
自社内で特別教育を実施する
- 自社に特別教育を実施する適任者がいる場合、社内で行うことが可能です。特別教育の講習担当者には特別な資格は不要ですが、専門知識と実務経験が必要です。
- 特別教育の内容は労働安全衛生規則で定められています。
外部機関で特別教育を実施する
- 各都道府県の登録講習機関が定期的に行っています。
- 社外受講でも、特別教育は事業者の責任のもとで実施されます
特別教育の内容

特別教育の内容は、労働安全衛生法に基づき、その業務に関する安全または衛生に関する特別の教育を行うことが定められています。具体的な内容は、安全衛生特別教育規程において、厚生労働大臣が科目や時間を定めています。
一般的な特別教育の内容は以下になります。
- 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること
- 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること
- 作業手順に関すること
- 作業開始時の点検に関すること
- 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること
- 整理、整頓及び清潔の保持に関すること
- 事故時等における応急措置及び退避に関すること
- 1~7に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
参照:厚生労働省(労働安全衛生関係の免許・資格・技能講習・特別教育など)
具体的な内容や手続きについては、各教育提供機関や関連法令をご確認ください。
特別教育の修了証の発行義務
外部機関で受講した場合、修了証が交付されますが、発行義務はありません。
自社内で実施した場合、修了証は発行せずに実施記録のみを保管します。
しかし、工事の手続き等で提出・提示を求められることもありますので、カード型修了証等常に携帯できる形で発行したほうが利便性が高いと言えます。
自社内でカード型の修了証を作成するというのはなかなか難しいということもあり、カード型修了証の発行まで提供している各実施機関を利用している事業者も多くあります
特別教育の修了証に記載すべき項目
- 修了証番号
- 特別教育の種類
- 交付日
- 証明者氏名
- 修了者氏名
これらの項目は、特別教育を受けた人がその教育を修了したことを証明するためのものです。
修了証は、特別教育を提供する機関によって形式が異なる場合がありますので、具体的な記載方法や項目については、各機関に直接ご確認いただくことをお勧めします。
また、特別教育の修了証には有効期限は定められていませんが、氏名の変更等があれば書き換えが必要になります。
修了証の発行は義務ではありませんが、特別教育を行った記録は3年間保存することが義務付けられています。
この記録には、受講者の氏名、受講した科目、受講した日時などが含まれます。これらの情報は、特別教育の適切な管理と記録保持に役立ちます。
特別教育の実施と記録保持は、労働安全衛生法に基づく重要な義務であり、適切な運用と管理が求められます。具体的な内容や手続きについては、各教育提供機関や関連法令をご確認ください。
特別教育の記録と保存
特別教育が行われた後、外部機関で受講した際には概ね修了証が発行されます。
しかし、自社内で特別教育を行った場合は修了証の発行は義務ではないため、発行しなくても問題はありません。なお、実施記録の保管は必ず必要になります。
特別教育の実施記録に記載すべき項目
これらの情報は、特別教育の適切な管理と記録保持に役立ちます。
特別教育の実施と記録保持は、労働安全衛生法に基づく重要な義務であり、適切な運用と管理が求められます。
具体的な内容や手続きについては、各教育提供機関や関連法令をご確認ください。
また、特別教育の実施記録は3年間保存することが義務付けられています。この期間を過ぎても、特別教育の修了証には有効期限は定められていませんが、氏名の変更等があれば書き換えが必要になります。
これらの情報は、特別教育の適切な管理と記録保持に役立ちます。具体的な内容や手続きについては、各教育提供機関や関連法令をご確認ください。
まとめ
特別教育は労働安全衛生法に基づき、業務に関する安全または衛生に関する教育です。
リスクを伴う特定の業務に従事する作業員には、特別教育の実施が義務付けられています。
自社での教育実施も可能ですが、外部機関での教育も有効な選択肢となります。
これらの機関は、「安全衛生特別教育規程」に基づいた専門的な教育を提供し、作業員の安全を確保します。また、教育の修了証や実施記録は、記載内容や保管期間に注意が必要です。
建設業は特定業務が多く、その全てに対する特別教育の実施が求められます。
そのため、外部機関の利用を積極的に検討し、抜けや漏れのない教育体制を整えることをお勧めします。安全な職場環境の確保に向け、適切な教育の実施を心がけましょう。
特別教育 受講申し込み受付中
【建設キャリア転職】施工管理求人のご紹介サービスを開始しました。
Web講座の外国語(ベトナム語・英語)字幕にインドネシア語が追加されました。
施工管理技士
特別教育・安全衛生教育関連
石綿関連講座
特別教育
- 足場の組立て等の業務に係る特別教育
- 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育
- ダイオキシン類作業従事者特別教育
- 粉じん作業従事者特別教育
- 石綿取扱作業従事者特別教育
- 自由研削といしの取替業務等特別教育
- フォークリフトの運転業務特別教育
- 玉掛けの業務に係る特別教育
- 高所作業車の運転の業務に係る特別教育
- クレーンの運転の業務に係る特別教育
- ローラーの運転の業務に係る特別教育
- コンクリートポンプ車特別教育
- 小型車両系建設機械運転特別教育
- 低圧電気取扱業務に係る特別教育
- 低圧電気取扱業務特別教育(通学1日間/全8時間)
- 低圧電気取扱業務特別教育(通学2日間/全14時間)
- フルハーネス型墜落制止用器具特別教育
- アーク溶接等の業務に係る特別教育
- 動力プレスの金型等の業務に係る特別教育
- 巻上げ機の運転の業務に係る特別教育
- 不整地運搬車の運転の業務に係る特別教育
- ボーリングマシンの運転の業務に係る特別教育
- ゴンドラ取扱い業務特別教育
- チェーンソーによる伐木等特別教育
- 高圧又は特別高圧電気取扱業務に係る特別教育
- 移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育
- 小型ボイラー取扱業務特別教育
- ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転の業務に係る特別教育
- ロープ高所作業者特別教育
- テールゲートリフター特別教育
安全衛生教育
- 丸のこ等取扱作業従事者安全衛生教育
- 有機溶剤業務従事者安全衛生教育
- 振動工具取扱作業者安全衛生教育
- 職長・安全衛生責任者教育
- 玉掛け業務従業者安全衛生教育
- クレーン運転士安全衛生教育
- 車両系建設機械運転業務安全衛生教育
- 刈払機取扱作業者安全衛生教育
- 移動式クレーン運転士安全衛生教育
- チェーンソーを用いて行う伐木等の業務従事者安全衛生教育
- 雇入れ時安全衛生教育
- 木造建築物解体工事作業指揮者安全衛生教育
- フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育
労働衛生教育
技能講習
能力向上教育(再教育)
- 足場の組立て等作業主任者能力向上教育
- 職長・安全衛生責任者能力向上教育
- 安全管理者能力向上教育(定期又は随時)
- 安全衛生推進者能力向上教育(初任時)
- 有機溶剤作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
- 特定化学物質作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
- 木造建築物の組立て等作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
- 衛生管理者能力向上教育(初任時)