
工事担任者とは?できることや種別による違いは?試験概要や取得のメリットまで解説!
公開日:2022年7月27日 更新日:2023年3月29日
工事担任者の総合通信(旧:AI・DD総合種)とは?
できることや試験概要、試験科目の免除まで解説

電気通信工事の経験を積みさらなるステップアップを目指す方のなかには、総合通信(旧:AI・DD総合種)の資格が気になる方もいるのではないでしょうか。
総合通信はアナログ・デジタル両方の通信工事に携われる、価値の高い資格です。
受験を目指す前には、総合通信の資格で何ができるか知ることが重要。
また総合通信の試験では、数多くの科目免除制度があります。
スムーズに資格を取得するためには、試験概要を把握することも重要です。
この記事では上記の点に触れ、総合通信について詳しく解説していきます。
目次
最終更新日:

工事担任者は施設に設置されている端末設備や電気通信設備と、有線の通信回線をつなぐ役割を担う資格です。
代表的な業務として、工事や監督が挙げられます。
通信回線には、アナログとデジタルの2種類があります。
両方の回線を扱えることは、総合通信ならではの魅力です。
総合通信の資格は、「第一級アナログ通信」と「第一級デジタル通信」両方の資格をあわせた効力を持ちます。
アナログ・デジタルを問わず、多くの通信設備工事に携われることは魅力。
たとえば以下の工事を担当することが可能です。
上記のとおり、幅広い工事を担当できます。
加えて、多くの回線を持つオフィスや工場の工事も担当可能。
総合通信の資格を持つことには、大きなメリットがあります。
総合通信は工事担任者の最高峰ですから、難易度は高そうに見えます。
実際の難易度はどうなのでしょうか。3つの観点に分けて、詳しく解説していきます。
総合通信は、第一級アナログ通信と第一級デジタル通信の両方に合格できるスキルが必要です。
数ある工事担任者の資格のうち、最も難易度の高いレベルに位置付けられています。
総合通信は、全員が3科目受験しないと合格できないわけではありません。
一部の科目を免除された方も多く受験しています。
受験した科目数による合格率は、以下のとおりです。
| 受験した科目数 | 令和元年以降の合格率 |
|---|---|
| 1科目 | 55~74% |
| 2科目 | 18~26% |
| 3科目 | 9~17% |
2科目・3科目を受験した方の合格率は、大変低くなっています。
このような方にとって、総合通信は難関資格といえるでしょう。
一方で1科目のみ受験すればよい方は、半数から4分の3の方が合格しました。
科目免除を受けられるレベルの受験者から見た場合、総合通信は難易度の高い試験とまではいえません。
通信に関する代表的な資格には、以下のものが挙げられます。
いずれも総合通信より上位の資格であり、試験のレベルも高くなっています。
特に「電気通信工事施工管理技術検定」の受験には実務経験が必要ですので、誰もが受験できる試験ではありません。
電気通信主任技術者を持つ方でも、1年以上の実務経験を要します。
資格そのものに加えて、出願自体の難易度が高いことも特徴的です。

総合通信の試験ではさまざまな科目免除制度を活用し、受験者の負担を軽減できます。
ここからは試験で認められている5種類の科目免除制度について、詳しく解説していきましょう。
工事担任者の認定学校で電気通信に関する学科や課程に属し、卒業・修了した方は「基礎」の科目免除が可能です。
認定学校には、大学や専門学校などが挙げられます。
在学していた学科や課程が認定学校に該当するかどうかは、電気通信国家試験センター「認定学校一覧表」ページでお確かめください。
総合通信の試験で科目免除を受けるためには、免除科目欄に「A」と記載されている必要があります。
また情報通信系の学部・学科に所属していても、「認定学校一覧表」に掲載されていない場合は科目免除を受けられません。
なお高校の場合、学歴による科目免除の対象は以下の2校2学科に限られます。
実務経験がある方は、基礎や技術の科目について免除を受けられます。
「基礎」の科目免除は、端末設備等の接続工事に2年以上携わっていれば可能です。
また以下の資格を持つ方は資格の取得後、端末設備等の接続工事に1年以上携わっていれば免除の対象です。
一方で「技術」の科目免除は、以下に挙げる2つの要件を満たさなければ対象となりません。
但し電気通信主任技術者の場合は、それぞれ1年6カ月の実務経歴があれば要件を満たせます。
| 要件 | 求められる実績 |
|---|---|
| その1 |
以下いずれかの業務に3年以上従事
|
| その2 | デジタル伝送路設備に端末設備等を接続する工事に3年以上従事 |
要件その1・その2とも、実務経歴と認められるための細かい要件があります。
詳細は電気通信国家試験センターのWebサイトでご確認ください。
一度合格した科目は、3年間の免除が受けられます。
科目合格の有効期限は、試験が実施された日から3年後の月末です。
この間には6回受験チャンスがありますので、3年経過するまでに残りの科目も合格できれば資格を得られます。
科目免除は、総合通信を受験した場合に限りません。
以下の試験を受験した場合も、科目合格後3年以内であれば対象です。
| 免除される科目 | 条件 |
|---|---|
| 基礎 |
以下いずれかの試験で「基礎」科目に合格した場合
|
| 技術 |
|
| 法規 |
|
他の資格をお持ちの場合は、科目免除が可能な場合も多いです。
なかには試験を受けずに資格を得られるケースもあります。
ここでは3つのケースに分け、免除される科目はなにか確認していきましょう。
第一級アナログ通信と第一級デジタル通信の資格を持っている場合、または両方の試験に合格した方は、所定の申請を行うことで総合通信の資格を得られます。
該当する方は、わざわざ受験する必要がありません。
工事担任者の資格を持つ方は、科目免除が受けられるケースが多いです。
たとえば「アナログ・デジタル総合種」を持っている方は「基礎」と「法規」が免除されるため、「技術」の科目に合格すれば資格を得られます。
以下の資格のうちどれか1つを持っている方は、「基礎」の科目が免除可能です。
また以下の表のうち、「○」で示した組み合わせを満たす方は「法規」の科目も免除できます。
| 資格 | 第一級デジタル通信 | DD第一種 | デジタル第一種 |
|---|---|---|---|
| 第一級アナログ通信 | (受験不要) | × | ○ |
| AI第一種 | × | × | ○ |
| アナログ第一種 | ○ | ○ | ○ |
電気通信主任技術者の資格を持つ方は、「基礎」と「法規」の科目が免除されます。
「技術」の科目に合格すれば、総合通信の資格を得られるわけです。
また以下の資格のうちどれか1つを持っている方は、「基礎」の科目免除を受けられます。
ここからは総合通信の試験概要について、解説していきます。
なお受験資格はないため、誰でも受験可能です。
試験は年2回、5月と11月に実施されます。
令和4年の試験日は、以下の通りです。
試験時間は科目ごとに、以下のとおりとなります。
| 科目 | 試験時間 |
|---|---|
| 基礎 (電気通信技術の基礎) |
40分 |
| 法規 (端末設備の接続に関する法規) |
40分 |
| 技術 (端末設備の接続のための技術及び理論) |
80分 |
複数科目を受験する場合は、科目ごとの試験時間を合計します。
たとえば全科目受験する方の場合は、試験時間が160分(2時間40分)となるわけです。
総合通信の試験は、以下に挙げる18の試験地で実施されます。
| 地方 | 試験地 |
|---|---|
| 北海道 | 札幌 |
| 東北 | 仙台、青森 |
| 関東 | 東京、横浜、さいたま、水戸 |
| 信越 | 新潟、長野 |
| 北陸 | 金沢 |
| 東海 | 名古屋 |
| 近畿 | 大阪 |
| 中国 | 広島 |
| 四国 | 高松 |
| 九州 | 福岡、熊本、鹿児島 |
| 沖縄 | 那覇 |
試験会場は、受験票で通知されます。
また試験地周辺の都市に会場が設けられる場合もあることに注意してください。
試験はマークシート方式で実施されます。
このため試験当日には、以下のものが必要です。
また試験の出題範囲は、以下のとおり広範囲におよびます。
| 試験科目 | 出題範囲 |
|---|---|
| 基礎 |
|
| 法規 |
|
| 技術 |
|
各科目とも100点満点で、60点以上取ることで科目合格を得られます。
試験の合格には、すべての科目で合格ライン以上の成績をあげることが必要です。
問題用紙に設問ごとの配点が記されていますので、ご確認ください。
試験手数料は8,700円です。
消費税はかかりません。

ここからは総合通信に合格するための学習方法について、詳しく確認していきましょう。
総合通信に適した学習方法は、以下の2種類があります。
はじめて総合通信を目指す方は、1番の方法で進めるとよいでしょう。
2回目以降のチャレンジとなる方は、2番の方法が効率的です。
以下のポイントにも注意し、学習を進めましょう。
合格に必要な勉強時間の目安は、今お持ちのスキルによって大きく異なります。
これまで通信分野に関する知識のない方がいきなり総合通信を目指す場合は、150時間前後の勉強時間が必要です。
一方で他の工事担任者の資格など通信に関する資格を持っている場合、必要な勉強時間はより少なくて済みます。
一例として「第1級陸上特殊無線技士」と「基本情報技術者」の資格を持つ方が、60時間程度の学習で合格できた事例もあります。
総合通信は、仕事をしながら資格を目指す方も多いでしょう。
以下のような方も、多いのではないでしょうか。
このような方は、通信講座を活用するとよいでしょう。
日本建設情報センターでは、工事担任者「総合通信」の講座を開設しています。
テキストと問題集に加えて、動画による講義も19時間分提供されます。
もちろん教材は、すべて専門家による監修付きなので安心。
Web教材はスマートフォンでも閲覧できるため、すき間時間も有効に活用し学べます。
総合通信はアナログ・デジタル両方の工事を行える、価値の高い資格です。
もちろん簡単に合格できる資格ではありませんが、取得によりあなたの市場価値もアップすることでしょう。
通信分野で働く方は、総合通信の取得を目指してみてはいかがでしょうか。

建築施工管理技士土木施工管理技士電気工事施工管理技士管工事施工管理技士電気通信工事施工管理技士電気工事士危険物消防設備士冷凍ボイラー工事担任者足場特別教育玉掛け特別教育高所作業車クレーン
建設業界で働きたい!実務経験なしでも取れる資格をご紹介
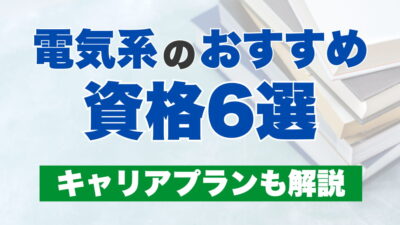
電気工事施工管理技士電気通信工事施工管理技士電験三種電気工事士消防設備士工事担任者
電気系のオススメ資格6選!キャリアプランも解説!

工事担任者の合格発表はいつごろ?発表方法や合格率、資格者証交付申請の方法まで紹介

工事担任者の年収は高い?仕事でできることや将来性、年収アップの方法まで徹底解説!

第二級デジタル通信(DD第三種)とは?難易度と合格率、合格するための勉強方法を紹介

工事担任者の難易度は高い?合格率や取得のメリット、必要な学習時間まで紹介

【2022年度】工事担任者の申込み方法は?試験スケジュールや合格発表までの流れを解説

工事担任者の試験はどう変わった?2022年度以降の試験方法は?
